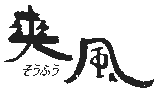
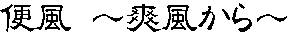
| 〜喫茶去〜 2011.3.10 |
|
最近、爽風のメ−ル上で「喫茶去」の言葉の意味について 何度かやり取りがありました。 皆様ご存じのように、これはもともとは禅の言葉であり、 茶道の中でも使われて行きました。 約1200年前、奈良時代に遣唐使や中国から 来朝した僧侶などによって喫茶の風習が日本に伝えられました。 その頃の茶は「団茶」であったと言われています。 その後平安時代、伝教大師が帰朝の際に 茶の実を携え帰り、 近江国(滋賀県)にこれを植えたのが始まりとされています。 当時は限られた特権範囲の人だけが飲み、 一般庶民階級とは凡そ無縁のものでした。 その後栄西禅師が宋から帰国する時 筑前国(福岡県)に茶の実を植え 京都の高山寺の明恵上人に茶の実を贈りました。 明恵は上手く茶の試植に成功し、 その後全国各地に移植され今日の茶の礎となりました。 もともとは薬として高価な飲み物でしたが 室町時代ごろには一般にも普及していきました。 このようにお茶自体も時代とともに変わって来ました。 今は「日常茶飯事」という言葉の中にも「茶」が出てきます。 「喫茶去」の意味もそれにつれて変わってきました。 「お茶でも召し上がれ・・・」ほどの意味でしょう。 「深く入って浅く出る」。 淡々とこだわることなくふるまい、日常茶飯事にお茶を飲み 当たり前の日常を過ごして行きなさいと いうことではないでしょうか。 淳子記 |
| 便風とは |
|
「びんぷう」と読みます。 意味は、「(1)追い風。順風。(2)便り。手紙。音信」を表します。 大辞林(国語辞典) |