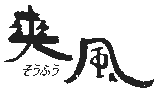
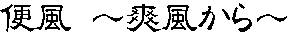
| 〜お歳暮〜 2004.12.05 |
|
「お歳暮」という慣習は日本固有のもので、世界で他に同じような習慣は無いそうです。 この「お歳暮」は、お正月に先祖の霊を迎え「御魂祭り」の御供え物や贈り物をした日本古来の習わしが始まりと言われています。 他家へ嫁いだり、分家した人が親元へお正月になると集まり御供え物を持ち寄ったのが始まりとも言われています。 正式には「事始めの日」というお正月をお祝いする準備を始める12月13日から12月20日までに贈るものでしたが、現在では11月末頃から贈られる方も多いようです。 贈るのが年内に間に合わなかったら関東地方では松の内である1月7日までに、関西地方では15日までに表書きを「御年賀」として贈るようです。 しかし、これをさらに遅れた場合は、松の内がすぎてから2月4日頃の立春まで「寒中お伺い」や「寒中御見舞い」として贈ります。 古い慣習として止めたいと思われる方も多いこの頃ですが、義理で贈るだけではなく、贈る相手の喜ぶ顔を思う浮かべながら贈るのも一つの贈り方かもしれません。 爽風では「お歳暮セット」のお申し込みを受け付けております。 詳しくは、爽風のトップページをご覧ください。 淳子記 |
| 便風とは |
|
「びんぷう」と読みます。 意味は、「(1)追い風。順風。(2)便り。手紙。音信」を表します。 大辞林(国語辞典) |