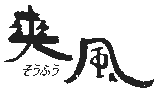
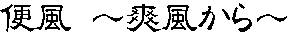
| 〜お茶の歴史〜 2004.9.18 | |||||||||||||||||||||||||
|
涼しくなると熱いお茶が美味しさを増します。 今回は《お茶の歴史》に少しお付き合い下さい。 中国唐の時代(618年〜907年)、日本は遣唐使を送り交流が始まりました。「僧行基、諸国49ヶ所に堂舎を建立。 これに茶の木を植えた。」--『東大寺要録』に書かれているそうです。 茶の歴史は日本では、中国に遅れること3500年後、奈良時代に始まります。 『万葉集』の歌の中にある「目不酔草」(メザマシグサ)は「茶」のことではないかと言われています。遣唐使によって持ち帰られた茶種はあちこちで植えられ始めました。空海もその中の1人でした。「疾病流行の際は薬用として茶を施した」と『空也上人絵詞伝都名所図鑑』に記されている通り高価な薬として代用もされていたわけです。栄西禅師が宋から帰って背振山に茶実を植え、さらに明恵上人に茶種子を贈ってから《茶》は広まっていきました。 その明恵上人の『茶十徳』が著されたのは鎌倉時代のことでした。
1000年以上も飲まれ続け、800年近くも前のこの四文字熟語が改めて胃袋に沁みます。茶の成分などを分析する科学が発達する前から《茶の効能》はいわれ続けてきたことなのでした。・・・つづく。 淳子記 |
| 便風とは |
|
「びんぷう」と読みます。 意味は、「(1)追い風。順風。(2)便り。手紙。音信」を表します。 大辞林(国語辞典) |